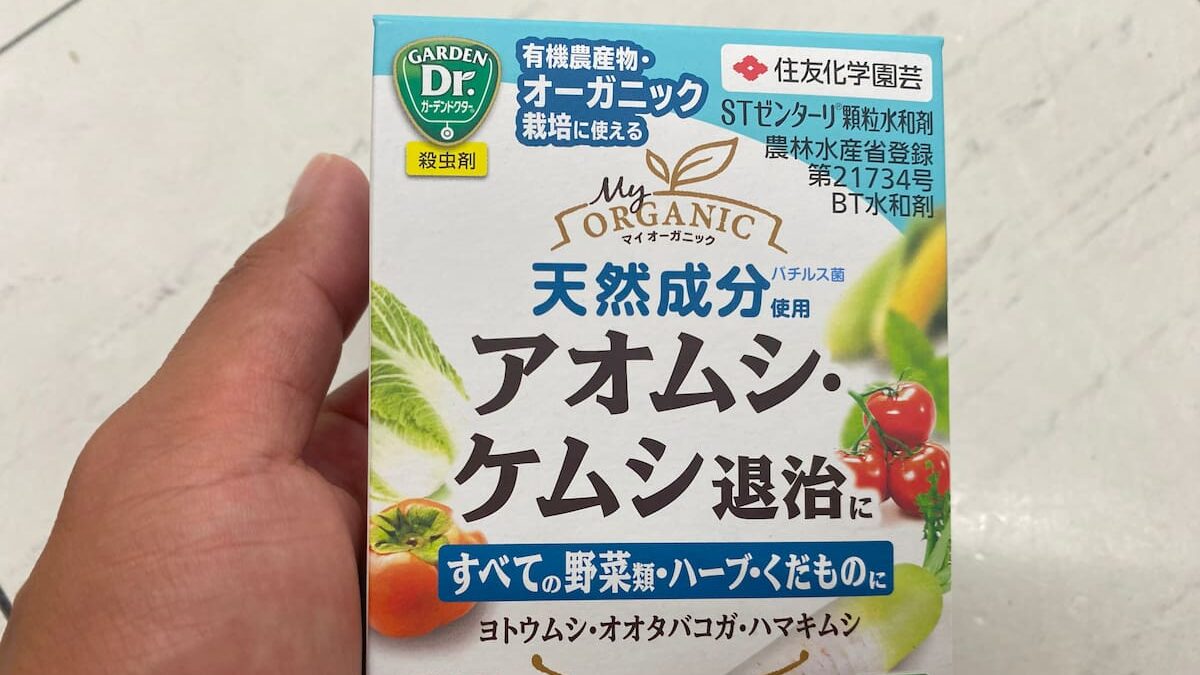【家庭菜園で気をつけたい】さび病の症状と対策方法ガイド

葉にポツポツとオレンジ色の斑点が現れることがあります。
それが「さび病」かもしれません。
さび病はさまざまな野菜や草花に発生するカビ由来の病気で、放っておくと葉が枯れたり収穫量が落ちたりする原因になります。
この記事では、さび病の正しい見分け方と対策方法をわかりやすく解説します。
さび病とは?
葉に「錆(サビ)」のような斑点が出来る病気
さび病は、カビ(糸状菌)の一種である「サビ病菌」によって引き起こされる植物の病気です。
胞子が風や雨によって飛び散り、周囲の植物に感染します。
名前のとおり、葉に「錆(サビ)」のような斑点ができるのが特徴です。
さび病の主な症状
| 観察箇所 | 症状の詳細 |
|---|---|
| 葉の表面 | 小さな黄色い点が現れる(初期) |
| 葉の裏面 | オレンジ〜赤褐色の粉状の斑点(胞子) |
| 進行後 | 葉が枯れる、変形する、落葉する |
さび病にかかりやすい野菜
さび病は風通しや湿度の影響を受けやすく、特に葉が細長く密集しやすい作物や、栽培期間が長めのもので多く発生します。
さび病はさまざまな植物に発生しますが、特に以下の作物で多く見られます。
ネギ属の野菜(ヒガンバナ科)
| 作物名 | さび病の特徴・注意点 |
|---|---|
| ニンニク | 葉にオレンジ〜赤褐色の斑点が出て、収量が減少しやすい。 |
| タマネギ | 特に湿度が高い時期に注意。葉が枯れ込む原因になる。 |
| ネギ(白ネギ・葉ネギ) | 連作や風通しの悪さで発症が多くなる。 |
| ラッキョウ | 密植によってさび病が発生しやすくなる。 |
| ニラ | 栽培期間が長く、夏場の蒸れにより発症しやすい。 |
| ワケギ・アサツキ | 香味野菜として人気だが、湿気でさび病が出やすい。 |
豆類
| 作物名 | さび病の特徴・注意点 |
|---|---|
| ソラマメ | 春先の湿度と高温で急激に発症することがある。 |
| エンドウ(スナップエンドウなど) | 葉に褐色の粉状の病斑が出ると、光合成が妨げられる。 |
葉物野菜
| 作物名 | さび病の特徴・注意点 |
|---|---|
| コマツナ・ミズナなど | 比較的発生は少ないものの、高温多湿や過密栽培では注意が必要。 |
さび病が発生しやすい環境
さび病は、湿気や風通しの悪さが大好きな病気です。
特に梅雨の時期や、葉っぱが込み合っている場所では、病気が広がりやすくなります。
ここでは、さび病が出やすい3つの原因について、やさしくご紹介しますね。
雨が多い時期(梅雨など)
さび病は、カビの仲間が原因です。
カビと同じように、湿った場所が大好き。雨の日が続くと、葉っぱがずっと濡れたままになり、そこにカビ(病原菌)がつきやすくなります。
梅雨の時期は特に以下に注意が必要です。
- 雨よけ対策をしたり
- 風通しの良い場所で育てたり
風が通らない
野菜の苗や葉っぱを狭い間隔で植えすぎると、風が通りにくくなってしまいます。
そうすると、湿気がこもってしまい、さび病が出やすくなるんです。
家庭菜園では、苗と苗の間に余裕をもって植えることが大事です。また、こまめに雑草を取るのも、風通しをよくするポイントになります。
病気の菌が土に残っているかも
実は、さび病の原因になるカビは、去年の枯れた葉っぱや土の中に残っていることがあります。
そうすると、今年植えた野菜にもまたうつってしまうんです。
この対策としては、
- 病気の出た葉っぱは畑の外に持ち出して捨てる
- 去年さび病が出た場所には、同じ野菜を続けて植えない(※これを「連作障害」といいます)
- 夏に「太陽熱消毒(たいようねつしょうどく)」をして、土をキレイにする
といった工夫が効果的です。

さび病の対策方法
発病初期の葉はすぐに取り除く
感染した葉は早めに取り除き、畑の外に処分します。
胞子が飛んで他の作物に広がってしまいますので出来る限り早くに対応してください。
風通しをよくする
過密になると葉が蒸れて、病原が繁殖しやすくなります。
株間や列間をやや余裕を持たせ、風の通り道を確保しましょう。梅雨時や蒸し暑い時期は、古い葉を剪定して風を通す工夫も有効です。
水やりは葉にかけない
葉が濡れると、さび病の原因となる菌が繁殖しやすくなります。
水やりは株元をねらって、そっと土にしみ込ませるように与えましょう。
ジョウロを使う場合は、ハス口(先端の穴の部分)を外すか、できるだけ地面に近づけて水が葉にかからないようにするのがポイントです。
ホースの場合も同じで、勢いを弱めて、株の根元を中心にやさしく注ぎます。
また、朝のうちに水やりを済ませるのが理想的です。日中に葉が乾くことで、菌の繁殖を抑えられます。
逆に、夕方や夜に水を与えると湿度がこもり、病気が広がりやすくなるため避けましょう。
病原菌を残さない
収穫後は病葉や茎、落ち葉をきれいに片づけ、土に残さないようにします。
過去に病気が出た場所にはすぐに同じ作物を戻さず、太陽熱消毒や畝を休ませる方法も取り入れましょう。

必要に応じて薬剤を使用
いくら気をつけていても、天候や環境によって「さび病」が出てしまうことがあります。
そんなときは、野菜に使える登録済みの殺菌剤を上手に活用してあげましょう。ただし、家庭菜園向けのやさしいタイプを選ぶのがポイントです。
初心者でも使いやすい薬剤の例
- ベニカXファインスプレー(住友化学)
→ トマトやナス、ネギなど幅広く使えるスプレータイプ。
病気と害虫の両方に対応できます。すでに発病した葉にも効果があり、希釈不要でそのまま使えるので便利です。 - サンボルドー(石原バイオサイエンス)
→ 銅を主成分とした「ボルドー液系」の殺菌剤。
さび病やべと病など、菌による病気に効果があります。自然由来で、野菜にも安心して使えるタイプです。 - ダコニール1000(住友化学)
→ 予防効果が高く、さび病のほか、うどんこ病や灰色かび病にも対応。
水で薄めて使うタイプですが、説明書通りに希釈すれば難しくありません。
使うときのポイント
- 必ずラベルを確認して、対象作物・希釈倍率・回数を守る
→ 薬剤ごとに使える野菜や使用回数が違います。 - 発病初期に早めの対応を
→ 病気が広がる前に、初期段階で使うことが効果的です。 - ローテーション散布で耐性を防ぐ
→ 同じ薬ばかり使うと効果が落ちてしまうことがあります。時々、違うタイプを使ってあげましょう。
いろはに農園のひとこと
さび病は、雨の多い時期にどうしても出やすい病気です。
でも、焦らず落ち着いて「葉を早めに処分」「風通しをよく」「必要なら薬剤でサポート」——この3つを心がけるだけで、野菜たちは元気を取り戻します。
まとめ
- さび病は湿気と風通しの悪さで発生しやすい
- 初期発見での葉の除去が重要
- 予防のための環境整備と衛生管理がカギ
- かかりやすい作物を知って、注意深く観察しましょう
ご家庭の菜園でも、さび病に負けない元気な野菜づくりを一緒にがんばりましょう。
症状の見分け方や効果的な対策についての疑問・感想をお寄せくださいね。