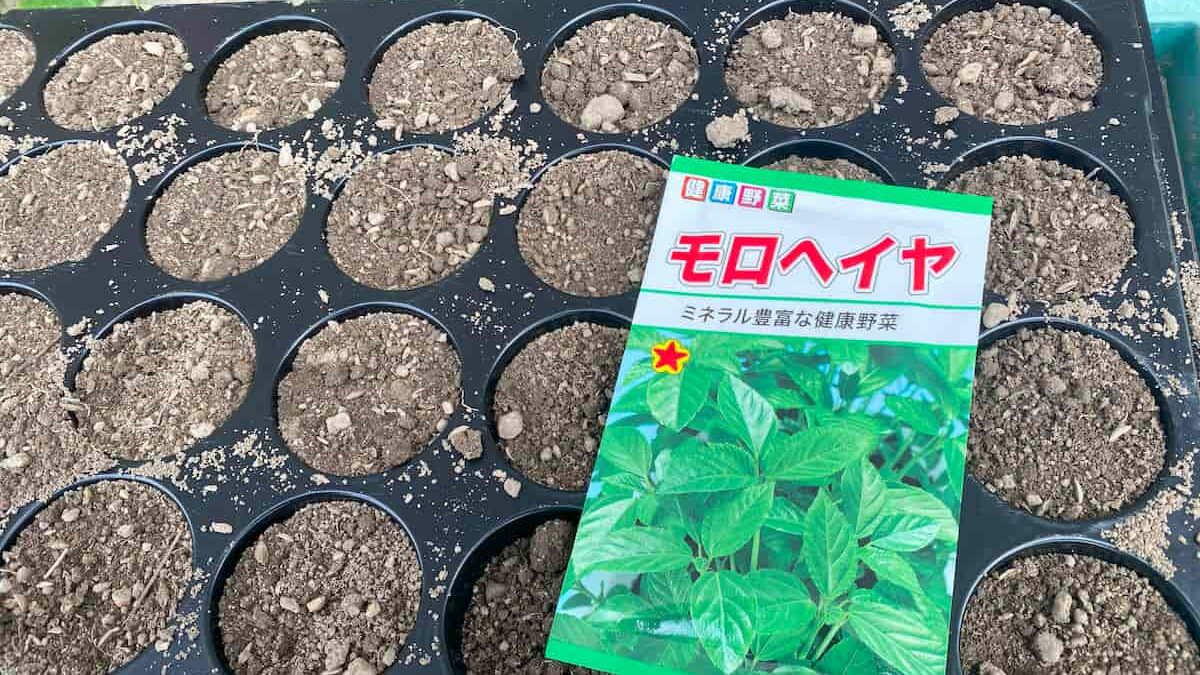【初心者でも安心!家庭菜園で楽しむ】小豆(アズキ)栽培ガイド

小豆は、赤飯やお汁粉に使われる、香ばしく甘みのある伝統的な豆。
実はこの小豆、家庭菜園でも手軽に育てられる作物なんです。
タネまきから収穫まではおよそ3〜4ヶ月と比較的短く、手間も少なめ。
初心者の方でもコツを押さえれば、自家製の小豆を収穫して、おいしい自家製あんこや煮豆を楽しむことができます。
この記事では、育て方を中心に、品種選びから土づくり、タネまき、収穫までをやさしくご紹介します。
気候と品種選び
生育適温とタネのタイプ
小豆の生育には、昼夜の平均気温が20〜25℃が理想です。気温の傾向によって、タネの品種は以下の2つのタイプから選ぶことができます。
夏小豆型
- タネまき:4〜5月/収穫:8〜9月
- 全国的に栽培できる定番タイプ。寒冷地にも向きます。
秋小豆型
- タネまき:6〜7月/収穫:9〜11月
- 気温の高い西日本向け。夏の暑さに強いのが特長。
土づくりと畝づくり
小豆は肥料が少なくても育ちやすいマメ科の植物です。とはいえ、基本の土づくりを丁寧に行えば、さらに元気に育ちます。
土壌の条件
- 水はけがよく、保水性もある土が理想。
- pHは6.0前後。酸性土壌の場合は石灰で中和しておきましょう。
- 元肥として、堆肥・化成肥料・苦土石灰をそれぞれ100g/m²程度施し、タネまきの2週間前までに耕しておきます。
畝づくり(露地栽培の場合)

- 幅70〜80cm・高さ10〜15cmの平畝が基本。
- 雨水が溜まりにくいよう、排水を意識したレイアウトにしましょう。
タネまき時期と方法
タネまきの時期
- 夏小豆型:4〜5月上旬
- 秋小豆型:6月中旬〜7月中旬
タネは1〜2日前に水に一晩浸しておくと、発芽がそろいやすくなります。
タネまきの方法
小豆は根をいじられるのを嫌う「直根性」の作物。根がまっすぐ伸びることで元気に育つため、直播き(じかまき)が一番おすすめです。
直播きの手順

1か所に3〜4粒ずつ、深さ3〜4cm

株間(株と株の間の距離)は約30cm
条間(列と列の間の距離)は40〜70cm

タネをまいた後は土を軽くかぶせ、たっぷりと水をあげましょう。
芽が出るまでは鳥にタネを食べられてしまうことがあります。
不織布や防鳥ネットをかぶせて、鳥から守ってあげましょう。
ポットまきが向いているケース
- まだ寒い時期(4月上旬など)
- 発芽の様子を観察したいとき
3号ポットに2粒ずつまき、本葉が4〜5枚になったら、根を崩さずに丁寧に植え替えましょう。
いろはに農園ではどちらも挑戦するのがオススメ
いろはに農園では、「ポットまき」と「直播き」の両方に挑戦する方法をおすすめしています。これは、初心者の方でも失敗が少なく、安定して収穫を目指せる育て方です。

まずはまだ肌寒い時期に、
ポリポットなどを使ってポットまきによる育苗を始めます。
室内やビニールトンネルの中など、温度管理がしやすい場所で、じっくり苗を育てていきます。
そして、気温が安定して暖かくなってきた頃に**直播き(地面への直接まき)**も同時にスタートします。
ここでポイントなのが、その後の苗の活用方法です。
栽培中のお世話とポイント
間引きと支柱
- 基本的に間引きは不要ですが、混み合うようであれば1〜2本に整理。
- 本葉が4〜5枚になったら、支柱やネットで支えてあげましょう。
土寄せと培土
- 8月頃になると株元がぐらつきやすくなります。
- 根元に軽く土を寄せることで倒伏防止になります。
水やり
- 地植えの場合、定着後は基本的に不要。乾燥しすぎる場合のみ対応。
- 鉢やプランターでは、土が乾いたらたっぷりと水やりを。
- 暑い日の朝か夕方に行うのがポイントです。
肥料と追肥の注意点
小豆はマメ科特有の窒素固定能力があるため、元肥のみで十分に育ちます。
ただし、成長が鈍くなったり、葉の色が薄い場合は…
- 花が咲く頃に、ぼかし肥や薄めた液肥をほんの少量与えてください。
植える際の注意点
小豆は同じ場所で続けて育てると、連作障害が起きやすい植物です。
同じマメ科(インゲン・エダマメ・ダイズなど)を続けて植えるのは避け、3〜4年あけて栽培するようにしましょう。
また、隣に植える植物にも注意が必要です。
ネギやニラ、ニンジンは生育環境が合わず、小豆の成長を妨げることがあります。
反対に、トウモロコシ・ダイコン・マリーゴールド・シソなどは相性がよく、お互いの生育を助け合う関係になります。
おすすめの組み合わせ
トウモロコシのそばに小豆を植えると、つるが支柱代わりに絡みつき、風にも強くなります。
マリーゴールドを一緒に植えれば、線虫や病気の予防にも効果的です。
収穫
タネ播きからおよそ3か月半ほどで、さやが茶色く乾いてきた頃が収穫の合図です。
若いさやを収穫すれば、やわらかい青豆としても楽しめます。
収穫したさやは、手でもみほぐすか、新聞紙を敷いて足で軽く踏んで脱粒し、しっかりと乾燥させましょう。完全に乾いたら、瓶や密閉容器に入れて冷暗所で保存します。
病害虫対策と鳥よけ
よくある病害虫
- 落葉病・萎凋病・茎疫病など
→ 水はけを良くし、発病葉は早めに除去。 - スズメガの幼虫:葉を食べる → 見つけたら手で捕殺
- アズキノメイガ:さやの中の豆を食害 → さやごと除去、防虫ネットで予防
- カメムシ・ハダニ・アブラムシなど:必要に応じて登録農薬や粘着テープで対応
鳥害対策
- 実が色づき始めたら、反射テープや不織布で覆って守りましょう。
まとめ:家庭菜園で小豆を育てる喜び
| ステップ | ポイント |
|---|---|
| 品種選び | 気候に合った「夏型・秋型」を選ぶ |
| タネまき | 気温と湿度に気をつけて丁寧に |
| 支柱・土寄せ | 株を支えて倒れにくくする |
| 病害虫対策 | 毎日の観察と早期対応が大切 |
| 収穫と保存 | 適期を逃さず収穫、乾燥・脱粒で長期保存へ |
小豆は、育てやすくて可愛らしい花も咲く、家庭菜園にぴったりの作物です。栽培を通して、季節のうつろいと共に、自然と暮らしがつながる喜びを感じてみませんか?
ご家族で一緒に育てれば、収穫のときにはきっと笑顔がこぼれるはず。手間をかけて育てた小豆で、おいしいお赤飯や自家製あんこを楽しんでくださいね。